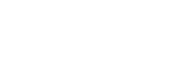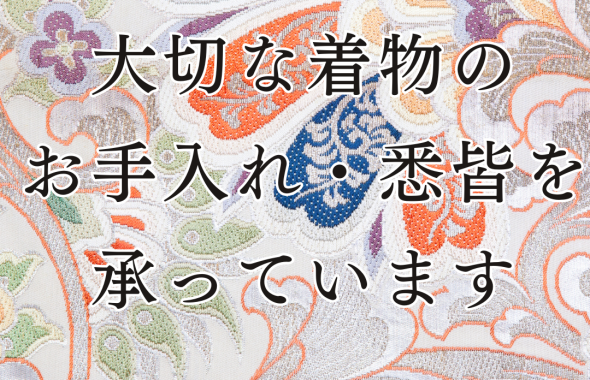一本の桑の木が着物になるまで ―― 着物・絹の物語と樋口屋の願い@埼玉県鴻巣市「着物振袖の樋口屋」
こんにちは。
樋口屋四代目社長の樋口寛司です。
いつもブログをお読みいただき、ありがとうございます。
蝉の声に本格的な夏を感じる毎日ですね。
連日の暑さに体調を崩されていないでしょうか?
ここ埼玉・鴻巣でも、日差しの強さに夏本番を実感しています。
暑さはまだ続きますが、皆さまも水分補給を忘れず、どうかお身体を大切にお過ごしください。
さて、今回のブログでは、成人式の振袖にも多く使われている「絹(シルク)」という素材について、そしてその絹を支える“養蚕”という伝統産業について、少しお話しさせていただきたいと思います。

「桑の木プロジェクト」に参加してきました
今年も、まだ肌寒さが残る早春の空の下、私は「桑の木プロジェクト」に参加してまいりました。
このプロジェクトは、日本の絹文化と養蚕業を守るために、養蚕に欠かせない“桑の木”を毎年植樹していく取り組みです。
私自身、着物という文化に携わる者として、絹の未来、そして日本の伝統工芸を次の世代に繋いでいく責任を感じております。
今日は、この時に学んだこと・感じたことを皆さまと共有できたら嬉しいです。
日本の美と誇り「絹織物」
絹織物は、日本の伝統工芸の代表格とも言える存在です。
その美しさはもちろんのこと、機能面でも優れており、古来から人々に愛されてきました。
最近では、大河ドラマ『青天を衝け』で養蚕農家に生まれた渋沢栄一の物語をご覧になった方も多いかと思います。
物語の中で描かれていたように、絹は日本の経済と文化の発展に大きく寄与してきました。
特に成人式でお召しいただく振袖に使われる絹は、その光沢と肌ざわりの良さで、他の素材では代えがたい魅力があります。
絹は、ただの“高級素材”ではなく、日本人の暮らしとともに歩んできた、歴史ある繊維なのです。
養蚕の歴史と現状
絹の原料となるのが、「蚕(かいこ)」が作る繭(まゆ)。
この蚕を育てる養蚕という営みは、なんと古代・邪馬台国の頃から日本に存在していたとされています。
特に江戸時代中期になると、絹の需要が高まったことを受けて、各藩が米に代わる産業として養蚕を奨励。
そこから日本全国に広まり、明治時代の工業化とともに飛躍的に発展を遂げました。
群馬県にある富岡製糸場が世界遺産に登録されているのも、その歴史的重要性を物語っています。
しかし、現在の日本では養蚕農家の数が激減。
2018年には全国でわずか293戸となり、ピーク時の数%以下にまで減少してしまいました。
高齢化や後継者不足、海外からの安価な絹の流入など、理由はさまざまですが、このままでは絹の原料である繭玉がすべて外国産になってしまう日も遠くありません。
桑の木に込める願い
そんな中で始まったのが、「桑の木プロジェクト」です。
この活動では、絹に関わる業者や呉服店の有志が毎年集まり、養蚕に不可欠な桑の木の植樹を行っています。
今年の2月に私が植えた一本の桑の木も、
7月初旬にはしっかりと葉をつけ、すくすくと成長してくれていました。
これから何年もかけて育つその葉が、いつか美しい繭を育み、
反物になって、そして素敵な振袖となって樋口屋に戻ってくる…
そんな未来を想像すると、胸が高鳴る思いです。
この小さな一歩が、やがて大きな流れになって、
日本の伝統と美意識を守り続ける力になることを信じて。
私も、来年もまた、必ず植樹に参加したいと思っています。
呉服店の仲間たちとも現地で再会し、ともに汗を流しました。
皆、その想いは同じ。
伝統と文化を次世代につなぐ、その一心です。


植樹当日
絹とともに、未来へ
私たち樋口屋は、人生の節目にふさわしい、
本物の着物をご提案することを使命としています。
その中で「絹」という素材が持つ意味を、少しでも多くの方にお伝えできればと思っています。
未来の晴れの日に、その着物が語る物語の一部として、
この絹が、そして養蚕の歴史が、皆さまの心に残れば嬉しく思います。